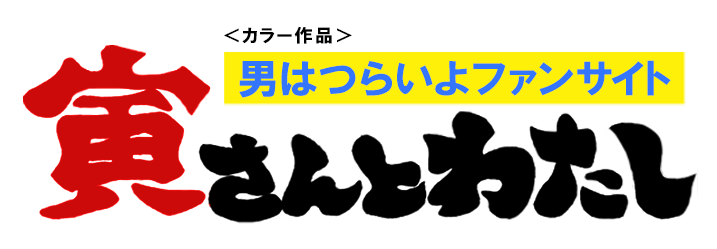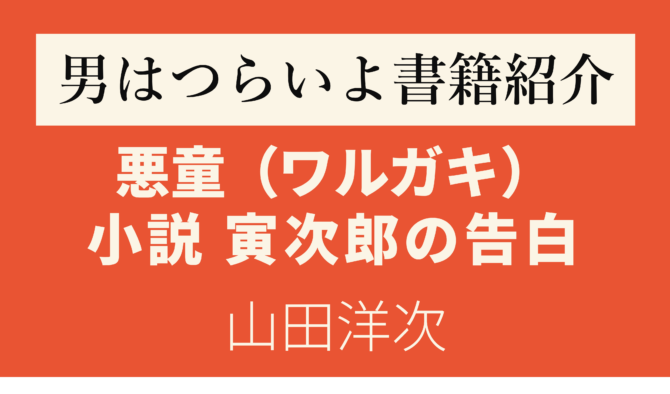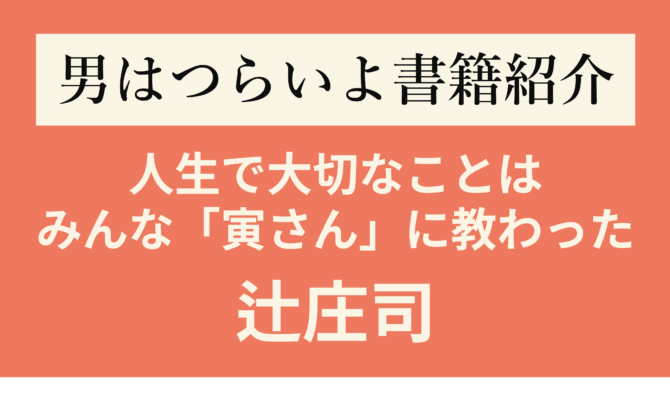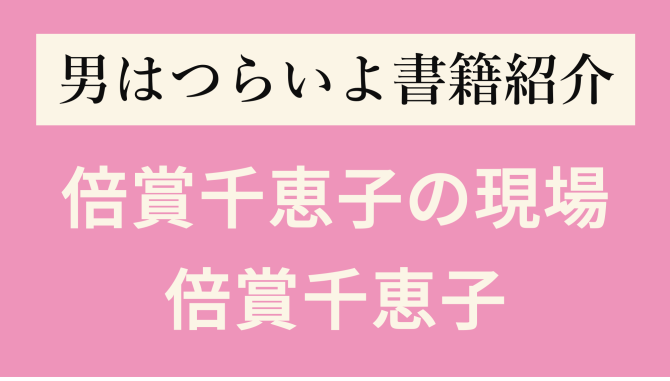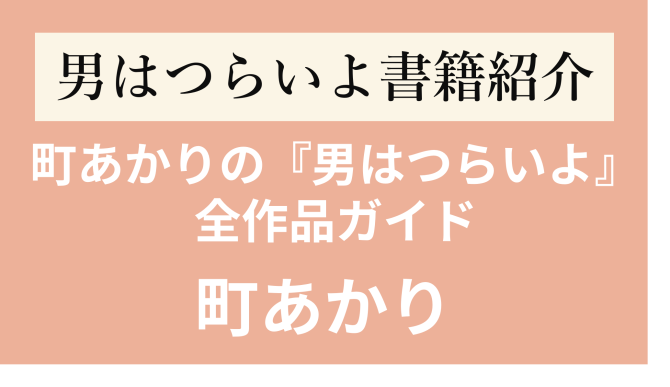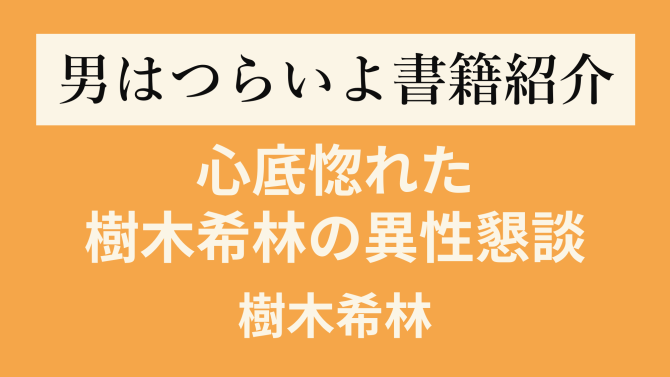渥美清は生前、多くの出版社から自伝の出版話を持ち掛けられたそうだが、すべて断ってきたという。そのため、本人が著したいわゆる「自伝」はこの世に存在しない。しかし、本人の口述をゴーストライターがまとめた「自伝的書物」ならば残っている。それが本書「新装版 渥美清 わがフーテン人生」である。
本書は、週刊誌「サンデー毎日」に連載された、渥美清の告白的半生紀を一冊にまとめたものだ。連載は第16作「男はつらいよ 葛飾立志篇」(1975年)の頃に始まっている。渥美清の存命中にも書籍化の話はあったようだが、本人の承諾が得られず、長らく書籍化されていなかった。渥美清本人としては不本意かもしれないが、彼の死から2カ月後の1996年10月、ようやく初版が刊行された。初版の解説に加筆を加えた今回の新装版の帯にはこのように書いてある──「名優がのこした唯一の自伝!」。
本書の元になっている、「サンデー毎日」の連載企画「聞き書きシリーズ」は、著名人一人につき全10回で完結するのが恒例だったようだ。しかし、渥美清の「聞き書きシリーズ」は読者からの反応も良く、全17回に延長された。好評の背景には、渥美清本人のやる気もあったのだろう。連載の企画打ち合わせにおいて渥美清は、「どうせ、やるのなら寅さん映画に負けない面白い連載記事にしましょうや。僕も一生懸命、協力しますから……」(「渥美清 役者もつらいよ」/吉岡範明 2P)と意欲的だったようだ。
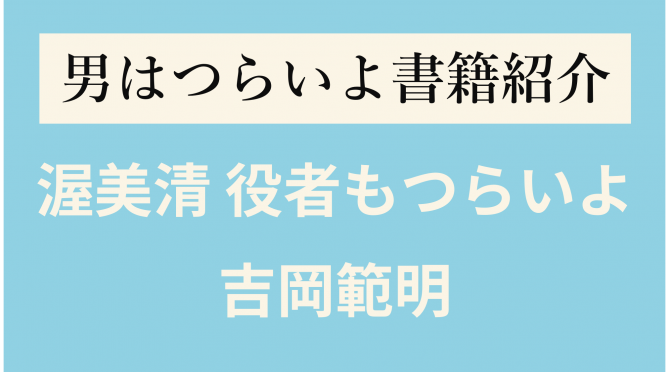
この言葉を裏付けるように、本書には渥美清の知られざるエピソードが満載である。ほどほどのエピソードでお茶を濁している感じは一切なく、彼の人生のハイライトがぎゅっと凝縮されている。俳優・渥美清の出自については、この一冊でほとんど押さえることができるだろう。
本書における渥美清の来歴は、大きく4つのパートに分けることができる。それぞれに軽く触れながら、渥美清の半生を振り返ってみよう。
- 幼少期から終戦後のフーテン暮らしまで
- 俳優デビューから結核闘病記、テレビ進出まで
- 主演映画『ブワナ・トシの歌』でのアフリカ旅行記
- テレビ版『男はつらいよ』の誕生から現在まで
渥美清の人生は、第二次世界大戦の影響を大きく受けている。日本が参戦した1941年当時、渥美清は中学生だったため、戦地への赴任ではなく軍需工場に学徒動員されている。同じく、軍需工場で働く女子学生たちを強烈に意識した思春期のエピソードは、マドンナの気を惹こうと奮闘する寅さんを彷彿とさせる。もはや教科書にそのまま載せても良いぐらいの、鮮やかで貴重な歴史資料である。
男子寮と女子寮との間の庭に、砲弾みたいな形をした消火栓がありました。わたくし、その消火栓を相手に、いつも膚身はなさず持っていました木刀で素振りをやっておりました。そのたびに木刀が消火栓に当たってカーン!!と響く。
なんのために、そんなことをしていたか申しますと、女子寮にいる女学生たちの関心をひくためだったのでございますよ。
春の宵のほの暗い庭で、女学生の心をとらえるために、木刀で消火栓を一生懸命たたいているニキビ面の少年──いま考えますと、男性の精液の臭いがするような情景ですが、まあ、交尾期に若い牡馬が鼻をふくらませて、ヒーンといななきながら前足で草をかっぽってる……そんな感じでございます。
「新装版 渥美清 わがフーテン人生」渥美清(23P)
やがて終戦を迎えると、渥美清は上野を根城として、不良少年たちとつるみ始めた。仙台で仕入れたヤミ米を東京で売りさばく「担ぎ屋」の仕事に精を出し、時には賭場に出入りすることも、吉原で女郎買いをすることも、酒に酔って電車内で喧嘩することもあったようだ。
そして、渥美清はこの頃、後の寅さんが劇中で披露する「テキ屋の啖呵売(たんかばい)」に出会う。テキ屋とは、人の集まる盛り場で怪しい品物を売りつける大道商人の一種。テキ屋のおじさんの格好良さに魅せられた渥美は、しょっちゅう彼らの後を追いかけ、啖呵売=セールストークを習得していったのだ。
渥美によると、テキ屋は「バサ」「ハズミ」「こまし」「ニガモノ」など、売り物や売り方によっていくつかのタイプに分けられるという。「男はつらいよ」シリーズの寅さんは、様々な品物を、様々な啖呵売で売りさばいていくが、元ネタはすべて本物のテキ屋たちのそれだったのである。テキ屋のタイプ別に啖呵売を諳んじて見せる渥美清の記憶力には思わず感心してしまう。本書のハイライトの一つである。
“こまし”専門のおじさんは、品物を売るときに決して膚着一枚になったりはしない。いつも背広をちゃんと着て、ネクタイをきちんと締めて、右腕に「出張員」という文字のはいった腕章を巻き、どっかの工場から、たったいま上野なら上野、浅草なら浅草の街角に来たばっかりのとこだといったようなたたずまいで、婦人服地なんか売っておりました。(中略)
「ここに運びましたる婦人服地は、本来ならばオーストラリアならびにスコットランドに輸出する品物であります。ところが染色、つまり、染めものの染めの関係で、染めの色にこのような失敗が出たのであります。しかしながら、それも、よォーく見なければ、その失敗はわかりません。(中略)まことに失礼ないいかたではございますが、まともなものなら、とてもじゃないけどみなさまの手の届きかねる品物であります。しかし、きょうは大棚ざらえも兼ねまして、あたしどもの社長が、日ごろからお世話になっている上野(浅草でもいい)の人たちに、この大道の一角を借りまして、ただでもいいからおすそわけして来い! とまあこう申しましたので、ここにお持ちしたわけであります。しかし、ただでとはいいますものの、無料でみなさまにさしあげるということはまことに失礼にあたります。形式上、いくら、いくらで──ということでおわけしたい。みなさま、せっかくのチャンスをお見逃しなきよう……」
「新装版 渥美清 わがフーテン人生」渥美清(46-47P)
その後、渥美清は、軽演劇を主宰する知人から誘われて舞台俳優となった。複数の劇団を転々としながら実力をつけ、いよいよ浅草フランス座の看板俳優に登り詰めた。しかし、ここで渥美清を襲ったのが、かつては不治の病として恐れられた結核である。
結核の診断を受けた際の動揺、手術室に向かう廊下の寒々とした光景、結核療養所で出会った患者たちのエピソードは、いずれもありありと情景が目に浮かぶものだ。この頃の出来事は渥美清の脳裏に消し難く焼き付いていたのだろう。ついさっきまで一緒に話をしていた患者仲間が電車に飛び込み自殺をした、長期入院で精神を病んだ女性患者が寝ている自分の顔面をベロリと舐めいったなど、寅さん風の明るい口調でいくらか聞きやすくなっているものの、どれも強烈なエピソードばかりである。
こうして、2年近くにおよぶ闘病生活を乗り越えて、渥美清は浅草フランス座の舞台にカムバックした。結核前の渥美清は、三度の食事が「焼き鳥と焼酎」という実に不健康な暮らしだったが、退院後は酒もたばこもきっぱりと絶った。その変貌ぶりに周囲からは「昔のアツミは、もうこの世にはいないんだよ。ウン、そう、あいつはもう死んだのさ……」と言われるほどだったという。
やがて浅草フランス座での活躍が電通担当者の目に留まり、渥美清はテレビ界、映画界に進出していく。映画では、オールアフリカロケで製作された映画「ブワナ・トシの歌」(1965年)に主演しており、この時のアフリカ旅行記が3章にわたって掲載されている。渥美清の実感に満ちたアフリカ旅行記は驚きの連続である。
なお、渥美清のアフリカ旅行紀については、書物「きょうも涙の日が落ちる」内にある、渥美清の口述ロングエッセイ「ぼくのアフリカ」にも詳しい。こちらには本書にないエピソードも数多く掲載されており、渥美ファンならば必見の内容になっている。
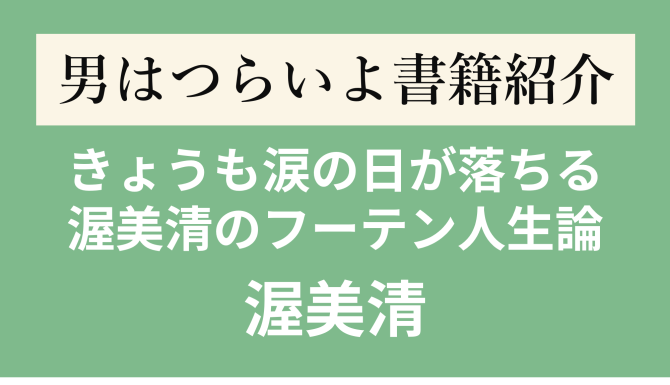
さて、本書のラストを飾るのは、やはり「男はつらいよ」の話題である。「男はつらいよ」は、元々テレビドラマから始まったことは有名な話である。渥美清は、山田洋次との初対面からテレビ版寅さんがどのようにして生まれたか、また、寅さんがハブに噛まれて死んだテレビ版の最終回とその反響について、さらには、初代おいちゃん・森川信の死について語り下ろしていく。
わたくし、フジテレビの方と一緒に、当時、赤坂の旅館を常宿にして、シナリオを書いていらした山田さんをおたずねいたしました。(中略)
二人でどんな雑談をしたかと申しますと(中略)わたくしの不良少年時代の思い出話で、そのうちにだんだんと上野広小路や浅草界わいで見聞きしたテキ屋のおじさんたちの話に移っていったのでございます。
雑談の場には、常に何人かの人たちが居合わせましたが、山田さんをはじめみなさんが、わたくし、あい語らいました話がバカバカしい内容だけど、なんとなく無責任でおかしかったのでございましょう。(中略)
「じゃあ、こういったテキ屋稼業をしてるおもしろい男を中心人物にして、ストーリーを固めることにしましょうか」
ま、結論は、そういうことになりましたが、それまで、わたくしの頭の中でいつも下町の裏街道を歩いておりましたテキ屋という名の渡世人は、そのとき、山田洋次さんの頭の中にさっさと引っ越していっちゃったわけでございますよ。
そして、山田さんの頭の中から、その渡世人がその後、わたくしの目の前に現れてきたときは、すでにフーテンの寅こと車寅次郎という名前をもらっておりました。(中略)「とらや」というだんご屋をやっている寅にとっては、おいちゃん、おばちゃんがいて、そこへ毎日、手伝いにくる利口でやさしいさくらという寅の妹がいる。(中略)
わたくし、山田さんから、そういうドラマの設定を説明されたとき、どうして、自分のあんな大ざっぱなくだらない雑談が……しかもバカ話が、こういうすばらしいものに化けてしまったのか? 実は今でも驚いているわけでございますよ。
考えてみますとやっぱり、役者と作者の違いは、ここにあるわけで、わたくし、あのとき、その違いというものをはっきり見せつけられたような気がしたのでございますよ。
「新装版 渥美清 わがフーテン人生」渥美清(157-159P)
本書の最終章において渥美清は、「寅さんシリーズで一番印象に残っている作品は?」「毎回寅さんを演じていて飽きないか?」「今後どんな役をやってみたいか?」などの質問に答えている。「男はつらいよ」シリーズが飛ぶ鳥を落とす勢いにあった頃、渥美清がシリーズの今後をどのように考えていたかを窺い知ることができる。
ところで、読者の中から、こんな質問がございました。
「寅さん映画をいつもおもしろく見てますが、惜しむらくは、同じパターンの繰り返し。だから、やがて飽きられる運命にあるんじゃあないでしょうか。(中略)渥美さんは、どう思いますか」
お答えいたします。もともと、わたくし、そう先々のことを考える頭をあいにく持ち合わせていないのでございますよ。同時に、そういったことは役者が考えるべきことではなくて、世間が役者に教えてくれることじゃあないかと思います。
「もう、いいんだよ。もう見たくないから、打ち切ってくれよ」
とおっしゃれば、ハイといって打ち切れば、いいと考えるのでございますよ。そして打ち切った後で、しばらく休んで、そして次のものにかかればいい、そう思うのでございます。
「新装版 渥美清 わがフーテン人生」渥美清(176P)
俳優が何を演じるべきかは、客が決めるもの。これは、舞台の上で観客の反応をダイレクトに浴びながら芸を磨いていった、渥美清らしい考え方である。渥美清は、「男はつらいよ」の新作が完成すると、映画会社の試写室ではなく、一般の観客が多く押し寄せる劇場にわざわざ足を運んで鑑賞し、その反応を確かめていたという。自分の演技が飽きられていないか、観客にしっかりと求められているかどうかを確認するための、俳優としての大事なルーティーンだったのだろう。
本書は全編にわたり、渥美清の話ことばが車寅次郎のような「寅さん口調」に変換されている。これについて、執筆に携わったインタビューライターの吉岡範明氏は、「寅さん映画を愛するファンを意識して、渥美さんの語り口を『……でございますよ』調のいわゆる寅さん口調にして文章化していった」(「渥美清 役者もつらいよ」/吉岡範明 2P)と述べている。
本書の冒頭は、車寅次郎のような仁義の口上から始まっており、素の渥美清による自伝を期待している人は多少の肩透かしを喰らうもしれない。しかし、本記事冒頭でも述べたように、渥美清はこの取材にかなりの熱量を込めて臨んでいたようで、内容の面白さは折り紙付きである。渥美清の半生紀を夢中になって読み進めていくうちに、寅さん口調もいつの間にか気にならなくなるだろう。