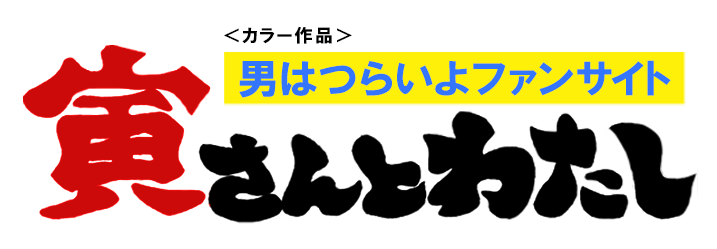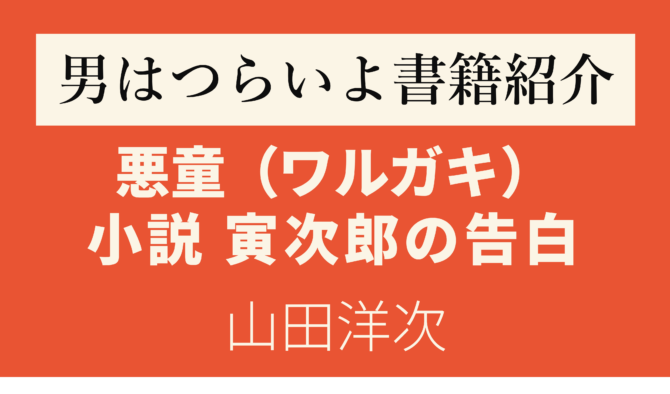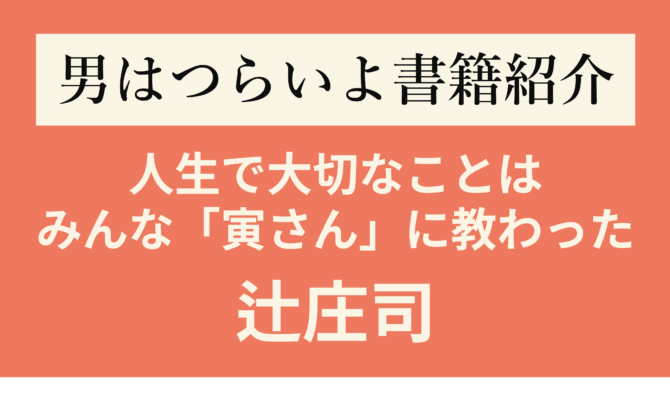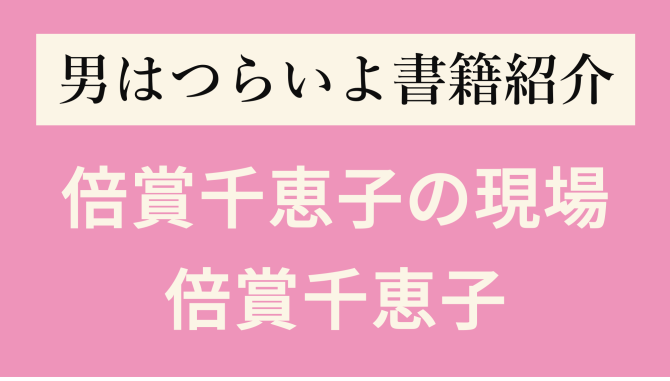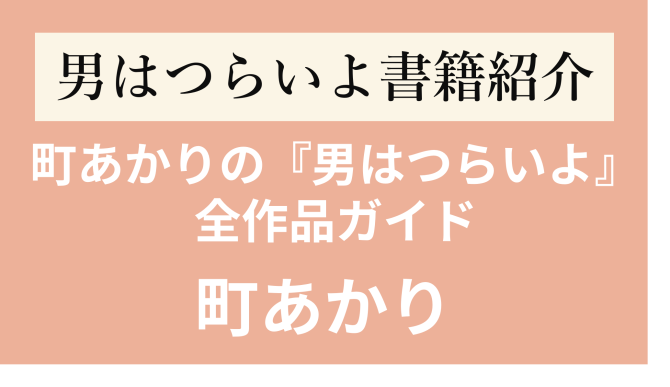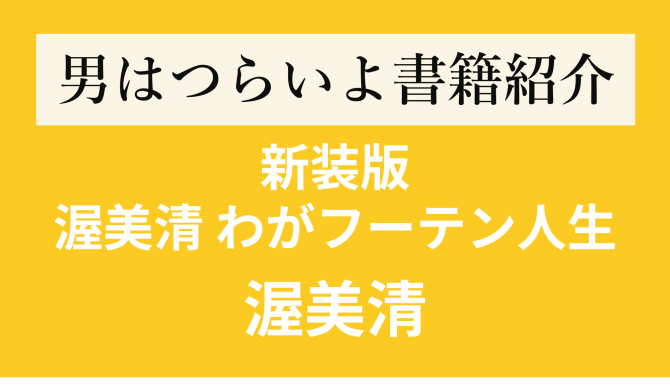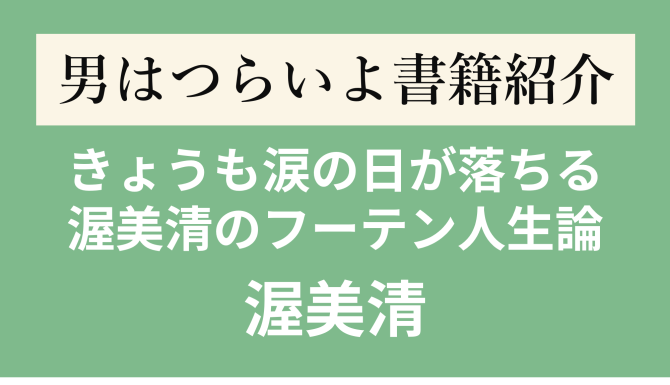本書は、月刊誌「婦人公論」で1976年(昭和51年)1月から12月の間に連載された、樹木希林による対談企画「異性懇談」を1冊にまとめたもの。ここに、渥美清と樹木希林の対談が掲載されている。渥美清はこの対談企画の第1回ゲストだった。
当時、樹木希林は「悠木千帆(ゆうきちほ)」という芸名で活動しており32歳。一方、渥美清は47歳で、第16作「男はつらいよ 葛飾立志篇」が公開されていた。(ちなみに樹木希林に改名するのはこの対談から1年後の1977年のこと。テレビ番組のオークション企画に出演した悠木千帆は、売るものがないという理由で自分の芸名を競売にかけた。芸名は2万200円で落札されたという)

樹木希林は、第3作「男はつらいよ フーテンの寅」で、寅さんが宿泊した旅館の女中役として出演している。寅さん以前にも2人はテレビドラマで何度か共演しており、樹木希林の見合い相手を渥美清が演じたこともあったという。プライベートでは「一緒に三流どころの花街や、浅草のゲイバーに遊びにいった」こともある仲だったそうだ。(朝日新聞デジタル記事より)
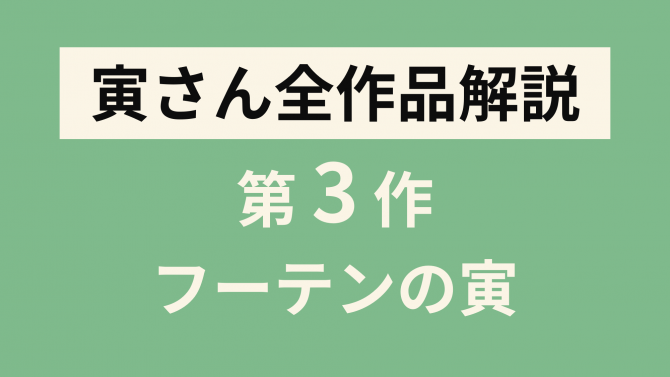
当時、樹木希林は渥美清を、「私生活というものを一切出さ」ず、「肩肘張らずにただ淡々と生きて」いる人物と見ていた。そんな渥美清が、なぜ車寅次郎をあんなに熱く演じることができるのか。その理由を知りたい樹木希林が、さまざまな角度から質問を投げかける形で対談は進む。
悠木 わたしが渥美さんに興味を持つのはね、たとえば女、それからお金、お金にまつわる住居だとか、宝石だとか、食べものだとか、そういうものに関して渥美さんが興味なさそうなのね。その部分がとても知りたいのね。
渥美 なるほどね。
悠木 私生活というのも一切出さないでしょう。それもけっして、むりやり拒否しているという感じもしないんですよ。渥美さんが、ぼくはこういうやり方でやるんだというふうに主張しているわけではなく、肩肘張らずにただ淡々と生きていらっしゃる感じがするの。
渥美 それほどのものでもないでしょう。
悠木 その淡々と生きているにもかかわらず、劇にどうしてあんなにカーッとできるんだろう。しかも、「男はつらいよ」も、劇にのめり込んでいるという気はしないんですね。何か一つ突き放した部分が魅力なの。
「心底惚れた」樹木希林(17-18P)
対談がどんな展開を見せるかについては、実際に本書を手に取ってご覧いただくとして、本サイトでは対談の中で明かされた渥美清の注目エピソードを2つご紹介したい。
エピソードの1つは、渥美清本人が明かす、「芸名・渥美清の由来」である。
渥美清は本名を「田所康雄(たどころやすお)」という。小学校時代からダトコロ、タショ、デンドコロなど、間違った読み方をされることが多く、さらに、クラスの中ではよく廊下に立たされる落ちこぼれであったことから、いつしか「田所康雄」という名前から離れたい気持ちが強くなっていったという。
そんなある日のこと。取るに足らない三文小説を読んでいた田所少年は、小説の中に登場する2枚目キャラクター「渥美悦郎」の活躍に心を奪われる。手元にあった鉛筆でその名前を紙に書き写し、「これは俺のペンネームだ」と言って家の玄関に張り付けたという。両親はにべもなくその紙を破り捨ててしまうのだが、その親の行為に対する反応が、田所少年の切実な変身願望を表していて切ない。
十いくつのときだからね。そのとき、そんなみっともないことするんじゃないよってはぎ取られて、パッと捨てられちゃったのね。自分で渥美悦郎に化身していきたいっていう願望、とても強かったね。何かツーンと涙ぐむくらい悲しかったね。そのとき、親に、何でこんなもの貼るんだって言われたときに。
「心底惚れた」樹木希林(16P)
その後、渥美清はコメディアン・俳優業を始めるにあたり、かつて両親に否定された「渥美」という名前を芸名として、「田所康雄」からの変身を果たした。自分ではない別の誰かになりたいという欲求は、俳優・渥美清の少年時代から心の内に強く根付いていたのである。
もう1つの注目すべきエピソードは、渥美清が考える「自分の死にざま」である。対談の終盤、渥美清は樹木希林からこんな質問を受ける。
悠木 たとえば自分が往生するときにいろいろな死に方が……望む人もあるし、考えもつかない人もいるだろうけど、渥美さんはどんなふうだと……?
「心底惚れた」樹木希林(29P)
これに対し、渥美清はこう答えている。
渥美 そういうといかにも役者じみてね、友だちにも前に言われたんだけど、雨足というのは、パーッと降ると白くピューッとはねるでしょう、下が。それがちょうどひさしのところからザーッと落ちるとピューッとはねるじゃないですか。ちょうどそこのどぶのところに斜めに首をつっこんでぼくが倒れていて、何かぼくはそのとき半長をはいているような気がするんだよね。ぼくのむくろの上にピシーッと相当篠つく雨で、ぼくはどぶに顔をつっこんで死んでいるという気が、とても前からしてしょうがないの。それが自分の最期だと。
「心底惚れた」樹木希林(29P)
どっかで、きっと役者やっていてもだめになって、馬券売り場かなんかではずれ馬券拾っていて、あるいは職業安定所かなんかのどぶのところで、こういうときは半長靴をはいて死ぬんじゃないかという、非常に自分で納得のいく終末にしているんですね。これはやっぱり役者だから、こういう終末の仕方に自分を持っていっているのよ。
「心底惚れた」樹木希林(30P)
押しも押されぬ映画スター・渥美清の最期としては、いかにも寂しく、また、到底実現しそうにもない最期だが、そのような最期に「自分を持っていっている」という表現に注目したい。渥美清は、自身の寂しい行く末を折に触れて想像することで、いつか車寅次郎が飽きられることへの心の予防線を張っていたのかもしれない。または、そうならないための戒めとして、このような最期をイメージすることを自分に課していたのかもしれない。
それにしても、自分の終末を語る際に、周囲に激しく降る雨や、その跳ね返りの水沫について、ここまで情景豊かに語るというのも変わっている。渥美清は何か伝えたい時、例え話をすることがよくあるが、その例え話のディテールの表現が豊かだったり、例え話の発想自体がトリッキーだったりするのだ。
この対談でも、よくぞそんな例え話を思いついたものだと感心する表現がいくつか見られる。本対談は、話し手の言葉をライターが整えることなく、ほぼそのまま掲載しているので、渥美清の話術のトリッキーさ、面白みがダイレクトに伝わってくる。特に「映画撮影の休憩中、急に晩飯の食材についてイキイキと話し始める俳優」の話は絶品である。話術の天才・渥美清の片鱗を知りたい方にとっても本書は良いテキストである。
なお、本書は渥美清のほかに、5代目・中村勘九郎、萩本欽一、つかこうへい、いかりや長介、山城新伍、米倉斉加年など、昭和の芸能や文化を彩った総勢12名のゲストが登場する。巻末解説でフリーライター・武田砂鉄が指摘するように、この対談企画の樹木希林は、かなり挑発的で攻撃的なインタビュアーである。ドリフターズのリーダー・いかりや長介氏などは、女性との肉体関係について根掘り葉掘り聞かれ、最終的には「みんなゲロさせられちゃった」と白旗を上げている。
「寅次郎には飽きませんか?」「奥さんもやっぱり気違いですか?」など、渥美清相手にもグイグイ攻める樹木希林のインタビュアーぶりはさすがである。対談相手が樹木希林だからこそ見えてくる、渥美清の素顔はぜひ本書でお確かめいただきたい。