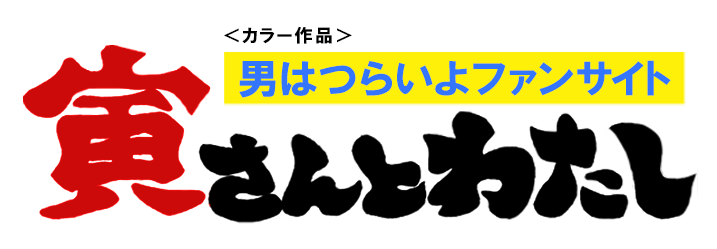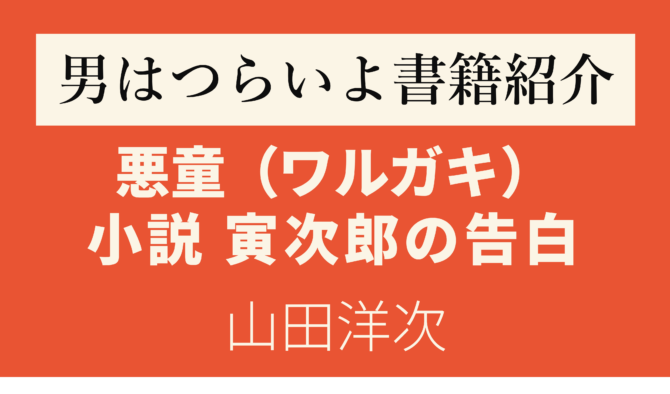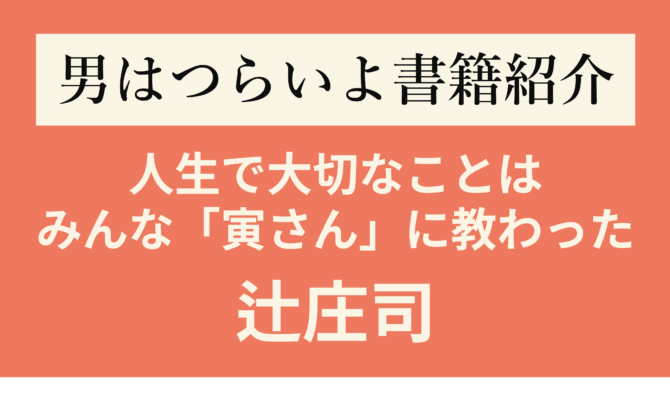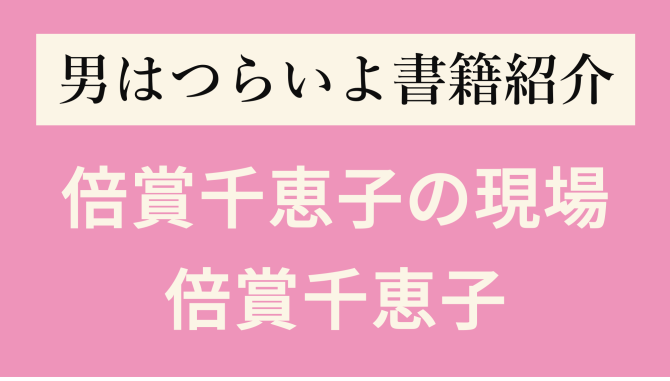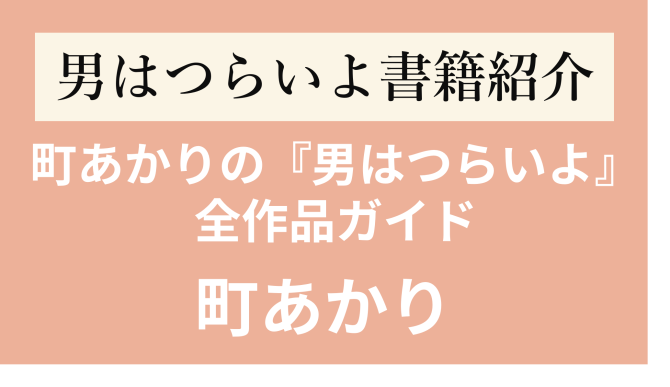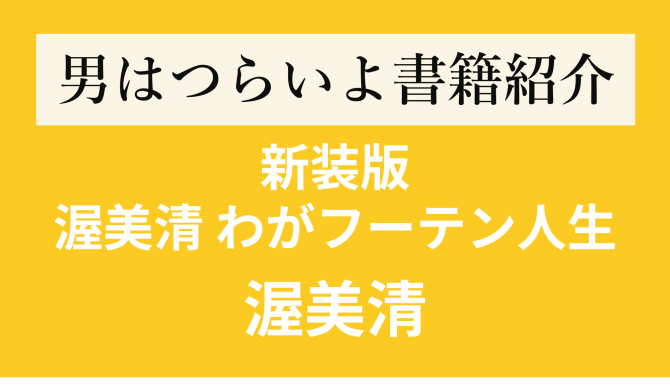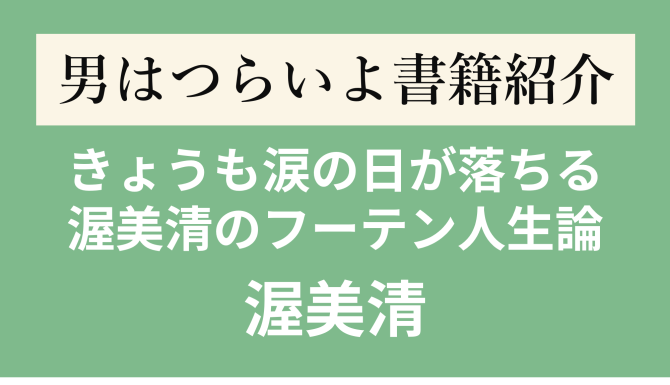元新聞記者である著者・寺沢秀明氏が、晩年の渥美清との8年間にわたる交友の様子を克明に記したエッセイである。
渥美清の死去後に出版された数多くの追悼本の中では、『おかしな男』『渥美清の伝言』などと並ぶ面白さで、渥美清のファンならば一読の価値があると思う。
その理由は2つある。
1つは、これまであまり明かされてこなかった渥美清のプライベートの過ごし方が詳細に記されていること。年1本の寅さん映画撮影以外の時間に、渥美清が何をして過ごしていたかを本書から伺い知ることができる。
もう1つは、晩年ガンに苦しめられた渥美清が、病や死に対してどのように向き合っていたかが記されていること。渥美清と著者の間で交わされた宗教的議論が、新聞記者ならではの高い文章力で詳細に記述されている点が素晴らしい。
私が知る限り、晩年、渥美さんは人知れず大きな苦悩を抱えていた。(中略)それは、少しずつそして着実に体を蝕んでいた病魔。それに伴う死の恐怖──。(中略)独り悩み、苦しみ、かつ、もがいていた。“救いの道があるなら”“わずかな時間でも心が休まるものならば”と、死に関する本を読み、思索を重ね、解決の糸口を求め、芝居を覗き、映画を見、講演に耳を傾けていたのではなかったか。その一つが私と共にした時間だったのだろうか。
(187-188P)
俳優・渥美清が生老病死にどのように向き合っていたか、また、彼の素の人柄に興味を持つ方には強くお薦めしたい一冊だ。
本書は大きく2つのパートで構成されている。前半は渥美清との交友の回顧録。後半は宗教的議論を中心にしながら、本書のタイトルでもある渥美清の死生観に迫っていく。
前半の回顧録はとにかく楽しい。「妙な出会いだった」(4P)と著者が振り返る偶然の初対面を経て、渥美清は「ちょっと付き合ってくれない?」と、映画鑑賞や観劇、果ては新居探し(を口実にした暇つぶし)など、プライベートの用事に著者をグイグイ引っ張りまわした。
時に厚かましく、時に人を食った言動で著者を手玉に取っていく様子は、まるで舎弟を手懐ける劇中の寅さんのようだ。寅さんと源公、寅さんと登、寅さんと為吉、寅さんと兵馬のやり取りを見るかのようで実に微笑ましい気持ちになる。
この前半パートからは、渥美清の観劇方法、映画論、芸術論、女性論、社交術、マスコミの処し方、オフの過ごし方など、あまり公にされていない渥美清のプライベートについて多くのことを知ることができる。渥美清のいい話が満載で、彼のマニアなら必読である。
共に映画を見、観劇し、美術館を巡り歩いた。春、桜が咲けば花見に出かけ、夏が来れば幽霊を見ようと古屋敷を覗きに足を運んだ。どこか子どもじみた行動ではあったが、どれも思い出深いひとときであり、私にとって終生忘れられない人生の一コマとなった。そして、今も誇りに思う。)
(まえがきより
さて、本書後半の渥美清の死生観については、若き日の渥美清を死の病から救った、ある売れっ子ストリッパーのエピソードから始まる。
渥美清は、浅草のストリップ小屋で幕間のコメディを演じていた頃、肺結核を患い入院した。1人また1人と仲間の入院患者が死んでいき、次はいよいよ自分の番か……と死の恐怖に襲われていたある日、突然医者から肺結核の特効薬であるストレプトマイシンを処方される。
医者は「ある人があなたのために……」とだけ語り、詳細を明かさなかったそうだが、この高価な特効薬を手配したのは、当時浅草で絶大な人気を誇った踊り子の女性だった、と渥美清は打ち明ける。
「俺の芸と才能を惜しむって、その彼女が体を売って……といっても、昔のような女郎になるって話ではなく、全盛期の人気と立場を引き換えに地方の劇場に移る契約を結び、その契約金で特効薬を手に入れてくれたんだ」
(144P)
健康を取り戻し、浅草の舞台に舞い戻った渥美清はもちろん彼女の行方を捜した。民放テレビ局の番組企画でも彼女を探したというが、結局行方は分からずじまいだったという。
「生かされているんだよ……俺は……だから変なことはできないんだ。彼女のためというのではなく、自分のためにも真っ当に生きて、その生き様が少しでもマスコミに拾ってもらって記事になる。それをどこかできっと読んで……喜んでくれる。そう思っているんだ」
(144P-145P)
渥美清は晩年ガンに苦しめられるが、専門家に「この状態で映画に出られたのは奇跡」と言わしめるほど、痛みに耐え、命の限りまで車寅次郎を演じ続けた。その行動を支えた原動力の一つが、この踊り子に「生かされた」という感謝の思いだったのかもしれない。
著者の寺沢氏は「人間は死んだら別の生命に転生し、永遠に生き死にを繰り返す」という死生観を持っている。ある時ふと語られたその死生観に惹きつけられた渥美清は、その後「この間の話、面白かったね」(139P)と言い、著者と会うたびに生と死、宇宙、神の存在などについて語り出したという。
こうした宗教談義が始まったのは1993年の事、と著者は振り返る。その2年前の1991年、渥美清はすでに肺ガンの宣告を受けていたから、著者が説く「人間の生命は永遠」という死生観は、当時の渥美清にとってすがるべき拠り所になっていたのかもしれない。
1993年、第46作『寅次郎の縁談』ロケ中のエピソードは強く印象に残る。瀬戸内海の志々島でロケをしていた渥美清は唐突に死の不安に襲われ、「ダメかもしれない。すぐに来てくれないか」(166P)と弱々しい声で東京にいる著者を電話で呼び寄せる。
翌日急いで駆け付けた著者と、渥美清が繰り広げた生死に関する語らいは禅問答のようである。以下に渥美清の問いかけを引用してみよう。
「君、前に人間は死んだら生まれ変わるって言っていたよね」
「それはわかりやすく言えばどういうことなんだい」
「どうして証明できるんだい」
「何度も言うようだけど、信じられないんだよ」
「そういう人はどうすればいい?」
「バカ言ってんじゃないよ」
「君は真面目に答えろ。死んで蘇った奴がいるか!」
(175-178P)
「人間は本当に生まれ変わるの?」としつこく食い下がる渥美清を安心させるため、著者はハッタリも交えて「生命は永遠です」とキッパリ自説を貫く。すると渥美清はようやく安心を得たのか問答を切り上げた。
その様子は、とらやのお茶の間での語らいに満足し、座を御開きにする車寅次郎の姿、そのまんまであり笑ってしまった。
「今日は何かとんでもない話を聞いた気分だ。でも、いい気分だな。なんだか急に眠たくなっちゃった。ありがとう、俺は寝るよ、寝ながらどこの星に生まれてこようか考えようっと……」
(185P)
最後は、寅さんの表情、口調になって、冗談を交ぜっ返しながら布団を被った。
渥美清の親友・谷幹一氏によると、渥美清はとても用心深い人物で、知り合う人のタイプを見極め、表面だけを見せる「A面」から、本音を語りあえる「Z面」まで、どの渥美清で接するかを瞬時に決めていたそうだ。
私はこれまでいろいろな書籍を漁り、渥美清の様々な「面」を知りたいと思ってきたが、本書にはこれまでどの書籍にも描かれなかった彼の姿があり、渥美清という人間の深さ、可愛さ、真摯さ、敬虔さ、が実感を伴って伝わってきた。
死生観に迫る後半部分に関しては、渥美清との交友回顧録という枠を飛び越え、宗教書のような雰囲気さえ帯びている。本書のあとがきで筆者は、『少しでも「生死」を考える人々の糸口になれば望外の喜びである』(213P)と書いているが、私にとって本書は十分にその役割を果たしたと思う。
最後に、渥美清が自身の人生を振り返った独り語りを引用し、本書の評論を終わりにしたい。自らの苦悩をひた隠し、喜劇役者に殉じた晩年の渥美清を思うと、深い嘆息が思わずこぼれてしまう。
「いったい俺は何のためにこんな思いをしてまで映画を撮らなきゃならないんだろう。眠れない夜中なんか、しみじみ考えてしまうよ。時には、まったく後先のことを考えないで、このままふっとどこかへ行ってしまったらどんなに楽だろうって……何回思ったことか。
病気をしてからはそんなことを思うことがあるんだ。これから先も何のために生きるんだろうって……実際のところ、わからなくなってしまうことがあるんだ。(中略)もし、この世に寅がいなかったら、こんなに人気者にならなかったら、自分はこんな思いをしなくてすむだろうって。寅で有名になり、豊かになり、寅でいい思いをしてきた。それなのに今、寅で辛い思いをしている。不思議だな。これも人生、楽あれば苦もあるってやつかい。
もし、過去の栄光・名誉と平凡な人生を選べと言われたら……交換できるとしたら、俺は喜んで栄光を棄てるね。浅草で遊んでいた無名の大根役者で結構。静かに……静かに、この世とおさらばできるなら、どれほどそっちの方が楽か」この言葉は心からの願望だったと思う。
(197P-198P)