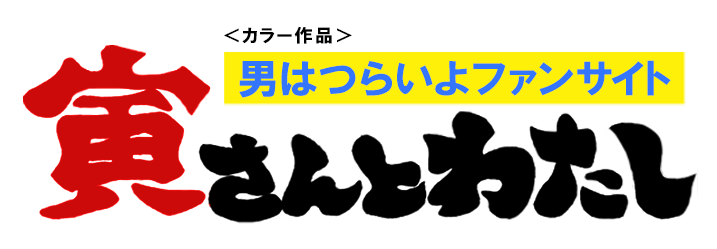小説家・滝口悠生さんは、2011年の処女作『楽器』で新潮新人賞小説部門を受賞。このデビュー作は川上未映子、大森望、豊﨑由美ら名だたる作家、評論家たちに絶賛されるなど、現在、日本の純文学界において大きな注目を集めている新人作家です。
2015年1月に刊行された最新作『愛と人生』は、映画「男はつらいよ」をモチーフにした異色の純文学作品であり、作中には熱狂的な寅さんファンもうならせる「男はつらいよ」論が展開されています。
圧倒的な描写力により、映画とはまた別の感慨をもたらす『愛と人生』は、滝口さんのどのような寅さん体験を元にして生まれたのか、うかがってみたいと思います。 (取材日:2015年4月7日)
「寅さん小説」に山田洋次監督から直々に感想をいただく
──『愛と人生』の反応はいかがでしたか?
おかげさまでいろいろな方に書評をいただきました。寅さん好きという方からのリアクションは案外少なくて、作品をきっかけに初めて寅さんを見たという方がほとんどでしたね。
寅さん好きだけに向けて書いた作品ではないし、とてもありがたいんですけど、意外にみんな寅さんを見てないんだなと(笑)。
──寅さん映画を見たことがない方の反応は、どんなものでしたか?
寅さんのディテールについてはみなさん元を知らないので、「そういうものなんだ」と読んでくれているみたいです。
作品を書くにあたってはマニアックになりすぎないよう気をつけながら、でも、マニアックな情報はちゃんとマニアックであることが伝わるよう意識的に細部を書いてます。自分には興味がなくても、ある分野についてものすごく細かく知っている人の話って面白いと思うので、そういう風に読んでいただければいいかなと。
──3代目おいちゃん・下條正巳に言及する作品論はとても鋭いと思いました。
あのあたりは、僕も下條正巳がシリーズに与えた功績っていうのをちゃんと認識しながら映画を見ていたわけではなくて。小説を書くにあたって、自分はこういう風に「男はつらいよ」を見ていたんだ、というのを規定しながら書いていったという感じです。対象についてぼんやりしたまま書くってすごく難しいことなので。
──本の帯に「山田洋次監督も共感」とありますが、監督はどんな感想を?
作品を発表する前に、講談社を通して山田洋次監督にゲラを送って、掲載許可のお伺いを立てたんです。それに対してわざわざハガキでお返事をいただいて、掲載のお許しと「面白い作品ですね」という感想をいただきました。帯のコピーはその言葉を拝借していて、「絶賛」とまではいかないけど「共感」なら書いていいんじゃないかと(笑)。

寅さんはちょっと傷んでるくらいのVHSで見るのがいい
──滝口さんが初めて寅さんを見たのはいつ頃でしたか?
小学生の頃、父親が寅さん好きだったので、テレビ放送を録画したビデオをよく一緒に見てました。子供の頃に家の中で流れているものって、子供としてはそのまま受け入れるしかなくて、「流れているくらいだからきっと面白いんだろう」と思っていました。実際、見てるうちに面白くなってきましたけど、子供の頃はその面白さに意識的だったわけではないですね。
──寅さんを意識的に、自発的に見だしたのは?
20歳過ぎぐらいですね。僕は高校を出てから5年くらいフリーターをしていて、物書きになりたいと思いつつ具体的に何をするわけでもなくフラフラしてたんです。その状態、境遇と、寅さんの生き方、考え方、世界の見方みたいなものがたぶん重なったんでしょうね。見始めたら面白くなって、繰り返し見てました。
──改めて見た寅さんはいかがでしたか?
面白かったですね。「あれ?結構いいんじゃない?凄いんじゃない?」みたいな。
社会と関わるようになってから寅さんを見ると、フィクションとはいえ、現実的な世界にああいう人間がいることの“凄み”みたいなものが実はあるなと。そういう再発見があって、一気に敬意というか、そういう対象として寅さんの生き方が見えてきましたね。
──それから全作品を順番にご覧になったのですか?
当時、まだ父親の録画したVHSが残ってたんですよ。それを週3、4日くらいのペースで「今日はこれ」「次はこれ」ってローテーションを組んで見て(笑)。テレビでやってない回とか、テープがダメになってしまって見られない回もあったので、ブランクもあるんですけど。
──テレビ放送を録画したVHSならではの鑑賞体験ですね。
そう。あと、僕はDVDがダメなんですよ、画質がキレイすぎて(笑)。僕にとってはVHSテープの、ちょっと傷んでるぐらいの感じで寅さんを見るのがベスト。何回も見てるとだんだんCMに入るタイミングもつかめてきますから(笑)。
いまだに「寅さんVHS全巻セット」で鑑賞する

たとえば音楽だと、このミュージシャンはレコードで聞きたい、このスピーカーで楽しみたいっていうのがあると思うんです。作品を受容する環境や条件って、体験にものすごく影響するじゃないですか。そこってあんまり問われないけど、実は重要なんじゃないかと。
寅さんはきっと受容の仕方がいろいろあると思うんですよね。僕らよりずっと上の世代は映画館の空気の中で見ただろうし、地上波テレビでリアルタイムにぼんやり見るのがいいっていう人もいるし、DVDがいいという人も当然いる。僕みたいにVHSがもうビヨビヨになってて「うちのビデオだとこの場面でザーってノイズが入る」みたいな見方もあるし(笑)。
そういう受容の体験って、寅さんに限らず僕のすごく興味のあるところで。どう聞くか、どう見るかって、実はあなどれない大事な要素だと思います。そのへんのことも本当は小説に書きたかったけど、そこまでやると完全な個人史になっちゃうんで(笑)。
──VHS鑑賞は、このご時世なかなかできないですよね。
ええ。でも僕はいまだにVHSで寅さん見てますよ。巨大な宝箱みたいな寅さんVHS全巻セットってご存じですか?それが家にあって(笑)。
ある日、家に帰ったらえらい巨大な荷物が届いてて、妻宛ての荷物だったからほっといたんですけど、実はそれ僕へのプレゼントだったんです(笑)。僕がVHSがいいっていうのを妻はちゃんとわかってたんです。うれしかったですね。
マイ・ベストは第25作『寅次郎ハイビスカスの花』
──滝口さんの一番好きなシリーズ作品を教えてください。
うーん、どの作品が一番かっていうのは難しいですよね。「今ならこの作品が好き」っていう風にタイミングによって変わるし、人にお薦め作品を聞かれて「初めて寅さんを見るならこれ」っていうのもあるし。
初めて見るなら『寅次郎夕焼け小焼け』(第17作)を薦めてます。個人的に好きな作品でいくと『夕焼け小焼け』『望郷篇』(第5作)『寅次郎夢枕』(第10作)かなあ。うーん、でも一番すごいなと思うのは『ハイビスカスの花』。一つあげるならあの作品かもしれないです。
──なぜ『ハイビスカスの花』なのでしょう?
まず、寅さんとは関係ないですけど、沖縄のあの雰囲気。沖縄の町や畑、風俗描写みたいなものがすごくいいなあって。あとは、病気のリリーを沖縄に訪ねて行く寅さんのエピソードもいいですし、途中水族館の女の子との意味わかんない恋とかもあって(笑)。
トピックは多いんだけど盛り込み過ぎというわけでもなく、最終作への大いなる布石として見ることもできるという。あの情報量の多さがすごく好きですね。
あとねえ、映画の冒頭で、博さんが町を歩いているリリーさんを見かけるじゃないですか。あの時のリリーさんの……
──もしかして、リリーさんが着てるヘンな服ですか?
そう!あのピタピタラメラメの服!最高ですよね(爆笑)。あの小話的なところもすごく好きです。
たしかあの町は小岩だったと思うんですけど、小岩のガチャガチャした風景から沖縄に行く振れ幅の大きさ、多様さ。だから非常にあの作品は好きですね。
時間と空間が圧縮される、旅先の風景描写シーン
──シリーズの中で好きなシーンはありますか?
どの作品ってわけじゃないんですけど、寅さんが柴又に帰ってきて、ケンカして、また出ていきますよね?テレビだとだいたいここでCMが入るんですけど(笑)。そのCM明けに、旅先の風景描写とBGMとしてクラシック音楽が重なるシーン、あそこが特に好きですね。
──マニアックですねえ(笑)。なぜあのシーンが好きなのですか?
映画の中で、寅さんが柴又を出てから旅先に着くまでの旅程って一切描かれてないと思うんですよ。でも、絶対電車で移動しているはずだし、ケンカのことを反省してるかもしれないし、まだ怒ってるかもしれないし。一方のとらやでも、その晩や翌日にどういう会話や時間が流れているのかって、一切描かれないじゃないですか。
要はあのシーンで時間と空間がぎゅっと圧縮されて、その圧縮の代替として風景描写があり、そこにおそらく山田監督が好きなだけのクラシックが重ねあわされるっていう(笑)。あのシーンにはいろいろなことを思わずにはいられないですよね。特に、寅さんシリーズを見込んでいる者としては、あの風景にすらいろんなものがフィードバックしてくるというか。寅さんをよくよく見返すようになってから好きなったシーンですね。あれって実はとても重要なシーンなんじゃないかと。
シリーズの中であれだけのバリエーションを描きながらも、旅先に向かう途中を一切描かなかった、それを48作で貫徹しているのは何かしらではあると思いますよね。
「男はつらいよ」一番の魅力は、問答無用のボリューム

──寅さんの魅力についてうかがいます。
うーん……難しいですけど……。ボリュームですかね。魅力と聞かれてボリュームっていうのも変ですけど、シリーズが48作もあるっていうのはすごく大きいと思うんですよ。
人も、場所も、出来事も、ぎゅっとまとめたらだいたい同じことが繰り返されている作品の中で、ほんの少しだけ微妙に違ういろいろなバリエーションが、あれだけのボリュームで変奏されているっていうのがすごいと思うんですよ。
人の毎日や、人生とかも、そういう風に同じことの繰り返しだったり、ちょっとずつ変わっていくことの積み重ねだと思うんですけど、わざわざあれだけの歳月と労力をかけて、同じことが48回も繰り返されていることの貴重さ、異常さ。でもその異常さが決して人事ではなくて、わが身に迫ってくるという。
どれか一作を見れば、あるいは、最初か最後の作品を見ればすべてがわかる、ということがない。あれだけの作品数とバリエーションがあるっていうのが、問答無用に大きいですよね。
──ちなみに、寅さんVHS全巻セットをプレゼントしてくれた奥さまも、寅さん好きですか?
奥さんは一緒に見てくれますけど、完全に付き合いですね、ハマりはしないです。どっちかというとヤキモキしながら見てますね、「なんでこの人いつもこうなの」って(笑)。寅さんはそういう視点で見たらよくないですよね、そうすると面白くない。ダメな人には全然ダメですよね。
──私の妻もまったく一緒です。「またこのパターン?」みたいな。
「はい、またこのパターンですけど?」みたいな。ははは。まったく一緒ですね。
寅さんを見ている時の心の動きは、小説執筆時のそれにとても近い
──小説「愛と人生」についてうかがいます。寅さん小説のプランが具体的になったのはいつ頃でしたか?
腹案としてはずっとあったんですが、講談社とある程度の長さの作品を初めてやるという時に、じゃあここで寅さんを出そうかなと。「寅さんDVDマガジン」も講談社だし(笑)。
──では、かなり以前から構想はあったと。
寅さんをモチーフにした作品が書けるのではないかということは、デビューする前から考えてました。ちょうど寅さんを毎日見ていた20歳過ぎぐらいの頃から。小説を書きたいと思いながらも毎日寅さんを見てたっていうのも変ですけど(笑)。
──寅さんを題材にしようと思ったきっかけは?
うーん、説明するのが難しいんですけど……。小説って、登場人物に見えるもの、聞こえるものだけを書くことも当然できますけど、でも、人は何かを見たり聞いたりしている時、頭の中で全然関係のないことを考えてたり、本当はもっと複雑な状態にあるはずなんです。
僕が思っている「小説感」というのは、その複雑さがすごく重要で、その複雑さに近いものを寅さんを見ている時にも感じていて。
──寅さんを見ている時に感じる「複雑さ」とはどういうことですか?
たとえば、寅さんを毎日見ていると、ある作品を見ながら別作品のワンシーンを思い出したり、自然と結びつけながら見るようになるんです。あれだけ長いシリーズですから、今見ている作品以外のほうが情報としては多いわけじゃないですか。この登場人物があの時はこう言ってた、それをふまえて今はこう言っている、というのを頭の中で勝手に関連づけたり、さらには演じている役者のことを考えたり、その役者の別作品における役柄を思い出したりとか。
だから、僕の感じている寅さんの面白さを伝えるとしたら、その作品のことだけを語ったとしても説明できなくて。他の47作品の何かを引っ張ってこないといけないし、寅さんを演じる渥美清の役者としての来歴もはずすことはできないし、他の山田洋次作品における倍賞千恵子の役柄についても説明が必要かもしれない。そういういろんなレイヤーが崩れてごっちゃになる感じは、小説における語りというものにすごく近いという意識があって。
僕が小説を書く時に大事にしたい複雑さと、寅さんを見ている時の複雑さがそのような共通項で結びついて、いつか寅さんを小説にできるんじゃないかと思っていたんです。寅さんを見ている時に自分の中で起こっていることは、小説の中である出来事や場面を書こうとしている時の感じと、僕の中ではすごく似てる、同じだという感覚がありましたね。
──小説家志望の頃は、実際に書くのではなく、そういうことに思いを巡らせていたと。
そうですね。書くというよりいろんな作品を読みながら、さっき言ったようなことをぼんやりと考えたりしていましたね。寅さんに関しても、ある作品を見ながら別作品の何かと重ねあわせたりすることの、捉えようのなさ、把握のできなさ、みたいなことをなんとなく小説と結びつけて考えたり。
人がある出来事や状態の中にいる時、どういう風に思うかってそんなに単純なことではないはずで。自分にそれがうまく書けるとは思っていなかったし、今でもどう書けばよいのやらわからないですね。
「美保純」をずっと「美保純」としたのは、自分でも説明できない
──本作品では「男はつらいよ」の作品世界と、現実世界の境界が極めて曖昧に進行していきます。このような着想を得たのはなぜですか?
映画って、一人の俳優が一人の役柄として登場するしかないですけど、映画を見た人はその内容を話す時に「あの場面で渥美清がさあ……」って言うじゃないですか。それって俳優と役柄がどっちとも言えない状態になっているんですけど、全然共有することができるんですよね。その状態を映画の中で表現するのは無理ですけど、小説なら結構できることなので、そこはなんらかの形で取り入れたいポイントだと思ってました。
特に、渥美清という俳優と、車寅次郎という役柄が、一人の人間の中でどっちがどっちだかよくわからないことになってるのは、小説を書く上ですごく面白いところだと思っていて。作品の第1章では、それをがっつりやったという感じですね。
──本作では視点人物がめまぐるしく変わります。視座の切り替えについては、構成を綿密に練られていたのでしょうか?
とても難しいところですね。視座の移り変わりを厳密にやることもできるんですよ、ここで視点人物が変わるから、このくだりでは「倍賞千恵子」ではなく「さくら」と呼ぶとか、あるいはその逆とか。厳密にやればいくらでもできるんですけど、でも、その厳密さにどれほどの意味があるのか、面白みがあるのかというのは微妙なところで。
──では、一人だけなぜか芸名で登場し続けた「美保純」は?
「美保純」をずっと「美保純」と書いたのは、自分でも説明できないんですよ、説明しろと言われても(笑)。そのほうがいいと思ったぐらいしか言えなくて。でも、それで十分通るし。なんでもありだと言うつもりもないんですけど、厳密じゃないほうが面白いし、パワーがある時もあると思うんで。
──視座の切り替えについては、書くに任せてということでしょうか?
そうそう。単なる不注意の時もあるんで(笑)。校閲の時に「ここはさくらではなく倍賞千恵子では?」みたいな指摘が入って、「あ、確かにそうだね」みたいなこともあるし(笑)。そのあたり完全には説明しきれないんですけど、だから面白いと思うんです。
第39作あたりは、倍賞千恵子や渥美清が一番美しくない時期だと思う
──作品には映画『寅次郎物語』の劇中人物が登場します。劇中人物の心境はどのようにして描かれたのでしょうか?
映画の中の状況を元に、この場面ならこの人物はこんな風に思うかな、というのを想像して書きました。そこは普段小説を書く時の想像力と同じですね。映像があるのでそれにも限界はあるんですけど。
──思春期の満男に対するさくらの苦悩は胸に迫るものがありました。劇中のなんでもないシーンから、あそこまで想像を広げられるのはすごいですね。
あの場面に限って言うと、39作のワンシーンだけで書いているわけではないんですよ。そのあとの42作から満男君シリーズが始まるんですけど、あのシリーズにおける満男君のさくらに対する態度が本当にヒドくって(笑)。それはさすがにあんまりだ、それではさくらが可哀想だ、ひいては倍賞千恵子もなんか可哀想だみたいな(笑)。その印象があの場面に逆流している感じはありますね。39作以降、その先がどうなるっていうのを知っているからこそ、ああいう内心の表現になったというか。
──シリーズ初期作品における、若い頃のさくらの印象も影響しているんでしょうね。
そうそうそう。あの時期はね、倍賞千恵子も渥美清も一番美しくない時期だと思うんですよ。美しくないっていうのは、単に年を取ったというだけでなく、映画シリーズの流れとしても一番疲弊してる時期じゃないかと。39作やその前後あたりって、渥美清もよくないし、倍賞千恵子もよくないし。でも、それがいいんですけどね(笑)。
女優とはいえ実名を出して、あまり美しくないみたいなことを書くのってためらいがないわけではなかったんですけど、でも長いシリーズにおける前があり、後ろがあり、っていうことを考えると、あのように書くことの抵抗はなくなりましたね。そこは割りと自信をもって書けました。
──映画の中では語られていない、柴又に向かう秀吉少年の心理描写も素晴らしかったです。
あのへんはむしろ普段の小説ってああやって書いてるので、すらすらと書けましたね。映像がないので自由に書けるっていう。
作品の題名を忘れられても、ある一節が読者の中に残りさえすればいい
──滝口さんの寅さん好きはお父さまの影響とのことですが、お父さまはこの作品をご覧になりましたか?
ええ読みました。感想も言ってましたけど、「よくわかんない」って(笑)。父親は古文の教師をやってたんです。だから、どうしても国語教育的な読み方から逃れられないみたいで。「作品のテーマは何だ?」って言われたんですけど、テーマは、別にないぞ?って(笑)。僕の作品には共通してこれと言い表せるようなテーマみたいなのはないですね。テーマっていうのがよくわかんないです。
もちろん読んだ人がこれがテーマだったと思うことは自由だし、そうやって個別の何かを見つけるのが小説を読むってことだと思うんですけど、それが何かと書き手に聞かれても、こちらもわからないとしか言えない。
──作品のテーマも、物語の構成も、執筆前にはあまりなかった?
全然ありませんね。まったくのゼロから始めて。書くに任せてっていう感じです。
──『寝相』など他の作品でも感じましたが、滝口さんはテーマよりも、局面における描写の美しさ、といったところに重きを置かれているのでしょうか?
おっしゃるとおりですね。僕も小説ってそういう読み方をするし、作品全体でどうかっていうのはさておき、あるシーン、ある場面が、読者の頭に残りさえすればいい。読まれ方として想定しているのはそういうことですね。だから、題名すら忘れて、「ずーっと前に読んだ小説のあの一節をもう一度読みたい、でも、あの小説なんだっけ?どの本だっけ?」みたいな(笑)。
そういうものになればいいなって思いますね。
(インタビュー終わり)